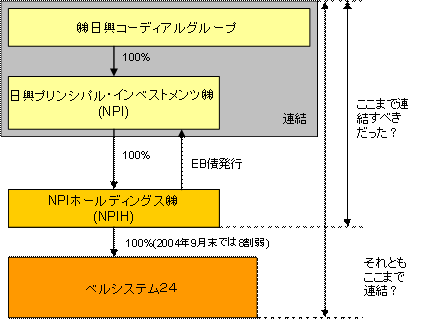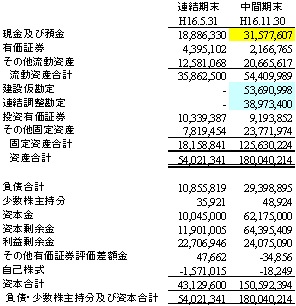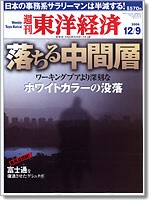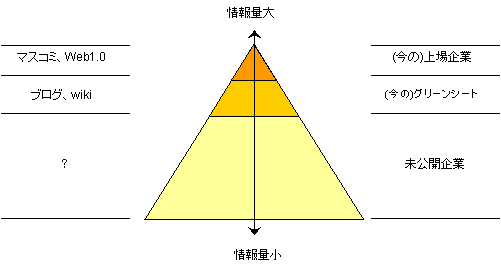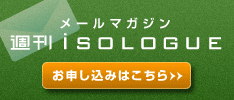日興コーディアルさんの件について、あちこちからコメントのリクエストをいただきましたが、特に今まで本件を注視してきたというわけでもないので、時系列で何が起こったかについて、頭の整理をしてみました。(以下、長文。)
---
2004年当時、CSKの子会社だった「ベルシステム24」ですが、2004年8月6日の日経金融新聞の記事、「CSK、ベル24株売却へ――『17日間』戦争の舞台裏。」によると、
「ベルが巨額増資を計画しているらしい」。CSKが情報を入手したのは一週間ほど前。二十日朝までにソフトバンクのかかわりなどをつかんだが、全容は明らかでなかった。
そして7月20日、ベルシステム24が「日興コーディアルグループ系の投資会社」に第三者割当増資をするリリースをして、CSKの子会社からはずれることになったわけです。ベルシステム24は、ソフトバンクグループのコールセンターの買収を発表。
日興コーディアルさん(以下「日興さん」)のプレスリリースによると、
2004年 7月20日
http://www.nikko.jp/GRP/news/2004/p_040720.html
株式会社ベルシステム24の第三者割当増資引受について
日興プリンシパル・インベストメンツ株式会社(株式会社日興コーディアルグループ の100%子会社、以下「NPI」)は、NPIの100%出資特別目的会社(NPIホールディングス株式会社)が株式会社ベルシステム24(本社:東京都豊島区、代表取締役社長 園山征夫、以下「ベルシステム」)の第三者割当増資を引き受けることを決定しましたのでお知らせいたします。
(中略)
第三者割当増資引受の具体的な内容は以下の通りです。
1. 引受株式数 : ベルシステムの普通株式5,200,000 株
2. 引受総額 : 104,260,000,000円(1株につき20,050 円)
3. 払込期日 : 2004年8月5日
前述の記事によると、同日、CSKは新株発行差し止めの仮処分を申し立ててます。
そして、
東京地裁は三十日、CSKの申し立てを却下。CSKは同日中に即時抗告、八月二日には定款違反行為の差し止めや議決権行使禁止などの仮処分を申し立て、全面的に争う姿勢を示した。
(中略)
潮目が変わったのは四日。ベルの増資引き受け先である日興側がCSKの持ち株譲り受けを申し出たのだ。提示した買い取り価格は四日終値より一〇%高い二万七千円。これは立会外取引のルールなどを参考にすると、ほぼ上限に近い。そのうえ同日、東京高裁がCSKの抗告を棄却。増資差し止めが事実上、不可能になったうえ、定款違反や議決権行使禁止などについての主張に対し否定的な見解を打ち出していた。
ということで、日興さんのリリースによると、
2004年8月5日
株式会社ベルシステム24の株式取得および第三者割当増資払込について
http://www.nikko.jp/GRP/news/2004/p_040805.html
1. 取得株式の種類および数 : ベルシステム普通株式1,580,000株
2. 取得価額 : 1株につき27,000円
3. 取得前後の所有割合 :(取得前) 0.00% (取得後) 32.25%
と、CSKから株式を取得することとなり、「親子ゲンカ」は幕引き。
7月20日にリリースされた増資(約1042億円)も実行されることに。
さらに、翌日、CSKは残りの株式の売却も決定して、他の株主も追随。
2004年8月6日
http://www.nikko.jp/GRP/news/2004/p_0408062.html
株式会社ベルシステム24の株式取得について
1. 譲渡人
・ 株式会社CSK(本社:東京都港区、代表取締役会長 青園雅紘)
・ 株式会社クオカード(本社:東京都新宿区、代表取締役社長 湯川英一)
・ CSKファイナンス株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長 青園雅紘)
・ ビジネスエクステンション株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長 井上啓司)
2. 取得株式の種類および数 : ベルシステム普通株式 計464,000株
3. 取得価額 : 計 12,528百万円
4. 取得前後の所有割合 :(取得前) 67.14% (取得後) 71.73% (*)
(*) 上記所有割合は、昨日払込期日の第三者割当増資による発行新株式数および昨日お知らせした株式譲渡分を加算して計算
この2004年8月6日の時点で71.73%(7,244,000株?要確認)を日興さんが保有するに至ったわけです。
そして、2ヵ月弱あとの2004年9月27日、TOBの実施を発表。
2004年9月27日
http://www.nikko.jp/GRP/news/2004/pdf/040927.pdf
日興プリンシパル・インベストメンツ株式会社による株式会社ベルシステム24の公開買付けの開始について
「2,770,731株を28,000円で買付け予定。
2004年9月24日までの過去3ヶ月における平均24,150.0円に対して15.9%のプレミアム。」
という条件。
1ヶ月後の10月28日、TOBの結果が公表されます。
2004年10月28日
http://www.nikko.jp/GRP/news/2004/pdf/041028.pdf
日興プリンシパル・インベストメンツ株式会社による株式会社ベルシステム24の公開買付け結果について
2,770,731株 買付け予定のうち、2,633,027株応募があった、とのこと。
9月27日付けで産業活力再生特別措置法の認定を受けているので、金銭交付による株式交換で100%子会社化を図ることに。
ベルシステム24の取引に関わる日興さんからのプレスリリースはここまでであって、今回問題になったデリバティブの取引については、ディスクローズされてないようです。(もしされてたら、教えていただければ幸いです。)
---
一方、同日2004年10月28日の新聞記事「ベル24株、公開買い付け終了、日興系の投資会社。(日経金融新聞)」によると、
ベル24は産業活力再生特別措置法(産業再生法)の認定を受けており、残りの株式は十二月に開く臨時株主総会での決議後にNPIが金銭交付による株式交換をする。ベル24はNPIの完全子会社になり、二〇〇五年一月半ばにも上場廃止の見込み。
と、株主総会と上場廃止日の見込みが掲載されてます。
さらに、このベルシステム24に投資をしたSPCの会計処理については、(今回、初めて問題が発覚したということではなく)、監査法人からも指摘があった旨が、一年ちょっと後の、2005年12月29日の新聞記事に載ってます。
中央青山、損益が不明確なSPC、日興に連結要請。(日本経済新聞)
このSPCは投資事業を手がけるNPIホールディングス(NPIH)。日興コーディアルの一〇〇%子会社である日興プリンシパル・インベストメンツ(NPI)が設立したペーパーカンパニーで、日興本体からみると孫会社にあたる。
NPIは昨年九月までに、コールセンター大手ベルシステム24の株式七百二十万株余りを取得。その際にNPIHとの間で、ベル株の値動きに応じて損益が変わるデリバティブ(金融派生商品)契約を結んだ。昨年九月末時点ではNPIに約百四十億円の評価益、NPIHには同額の損失が生じていたようだ。
グループ内で損益トントンとなる取引だが、SPCであるNPIHは連結対象外。このためNPIの利益だけが決算に反映された。日興の二〇〇四年九月中間決算では投資事業の経常利益が百八十億円弱と前年同期の六倍強に急拡大した。
現在の会計ルールでは投資事業に関連して保有している株式は連結対象にしなくてもよい。だが中央青山は「不透明な会計処理と受け止められかねない」として、〇六年三月期決算ではNPIHを連結対象にするよう求めた。今回の要請をきっかけにSPCの会計、情報開示ルールを巡る議論が活発になりそうだ。
日興コーディアルグループの有村純一社長は「ベル株を巡る会計処理はルールに即していると認識している。今後、会計ルールが変われば適切に対応したい」としている。
翌年、2006年1月12日の日経新聞「買収ファンドの実相(中)近くて遠い回収の道――割安な案件も少なく。」では、
コールセンター大手のベルシステム24の株主資本が〇五年七月に千三百億円、率にして九割弱減った。同社を買収した日興プリンシパル・インベストメンツ(NPI)から自社株を買い戻し、消却したからだ。
日興コーディアルグループ系のNPIは〇四年、総額二千四百億円でベルを買収した。ベルの大株主だったCSKとの法廷闘争の末、一千億円超の第三者割当増資を引き受けた経緯がある。増資資金を上回るおカネがNPIに戻った。
とありますので、最終的には、日興さんは「このベルシステムの取引で儲かった」ということのようです。つまり、経済的に損失が出ているのを粉飾で隠した、といった類の話とは違う模様。
(だけど、「どうせ儲かるんだから、早めに計上してもいいじゃないか」ということは無いわけですので、最終的に儲かったかどうかと、会計処理として適切だったかどうかは、また別の話。念のため。)
2006年1月27日の日経新聞朝刊の記事「日興コーディアル、経常益2.2倍、4―12月、手数料伸びる。」では、
自己資金投資はベルシステム24など投資先企業の株式を売却したことなどで二割強の増益になった。自己資金投資は連結対象外の特別目的会社(SPC)を通じて取引しており、情報開示が不十分ではないかとの指摘もあるが、「会計ルールに即しており、SPCは今後も連結対象外として取り扱う」(日興コーディアル)としている。
と、SPCを連結する気はない、という主張でらっしゃっいました。
2006年1月31日の日経金融新聞「大手証券3社――会計処理にばらつき。」という記事でも、野村、大和、日興、のうち、
米国会計基準で連結決算を作成する野村
については処理が最も保守的で、「誰が最終的に利益を享受するのか」という観点で連結・非連結を判断、SPCも投資先も連結対象としており、また、大和についても、
日本基準採用だが、非連結なのは投資先企業だけ。「SPCは株式取得の器であり、投資育成することはない」(財務部)として連結対象だ。
としているのに対して、
日興はSPCも「投資スキームの一環」(財務部)と判断し、連結対象から外す。二千四百億円で完全買収したベルシステム24のケースでも、連結対象外のSPCが株式を取得したため、日興本体の貸借対照表にはベル株そのものは計上されなかったもよう。
SPCを非連結にすると損益にも影響する。二〇〇五年三月期にSPCはベル株で償還できる他社株転換社債を発行。それを日興の連結対象の投資会社、日興プリンシパルが購入するといったデリバティブ取引を実施した。その後、日興プリンシパルが公開買い付けを実施したのを受けて上昇したベル株に連動する形で、デリバティブ取引に百数十億円の評価益が発生。これが日興の同期決算で増益要因となったもよう。SPCが連結対象ならグループ内取引として損益は消去されたと考えられる。
ということで、利益計上の妥当性についての疑問は、1年前にすでに明確に指摘されてました。
こうしたプレッシャーを受けてか、2006年4月27日の日本経済新聞朝刊の記事「投資事業の特別目的会社、日興、連結対象に、透明性高める。」では、
日興コーディアルグループが投資事業で利用している特別目的会社(SPC)を二〇〇六年三月期決算から連結対象としたことが明らかになった。現在の会計ルールでは投資事業に関連して保有している株式は連結対象にしなくてもよいとの規定がある。ただ、SPCの情報開示拡充の議論が進んでおり、連結範囲を広げ透明性を高めた。
(中略)
完全買収したベルシステム24の場合は、一〇〇%出資にもかかわらず、同社株を持つSPCが連結対象から外れ、財務内容が見えにくいとの指摘が出ていた。
と、今後については連結する方針を打ち出してます。
(ただ、過去分の処理は訂正してません。)
そして、2006年12月16日の日本経済新聞朝刊の記事、「不適切な利益、日興が計上――特別目的会社連結外し、損失、反映せず。」に至って、
日興の子会社である日興プリンシパル・インベストメンツ(NPI)は二〇〇四年八月、一〇〇%出資しているSPCのNPIホールディングス(NPIH)を通じ、コールセンター大手ベルシステム24の株式を大量に取得した。
一方、NPIとNPIHはベル24の株価によって損益が変動するデリバティブ(金融派生商品)取引を締結。その後、ベル株が上昇したことでNPIは百四十億円程度の利益を上げ、親会社である日興コーディアルの〇五年三月期連結決算に計上した。
この金融取引で、NPIHはNPIと同額の損失を抱えたもよう。いずれもグループ内部の取引なので、本来なら連結決算上は利益・損失を相殺するのが通常の処理だ。ところが日興は評価益を計上しながら、損失分については連結決算に反映しなかった。
ということになったわけです。
デリバティブの中身は?
この「デリバティブ」の内容がよくわかりませんが、本日行われた記者会見の様子を又聞きしたところ(つまり以下の内容は「要確認」ですのでご注意ください。)、日興さん側の主張としては、
「2004年8月にEB債を発行する予定にしていたが、実務上の処理が遅れて、発行が9月末になってしまったが、この間に株価が上がったので、NPIに利益が発生。しかし、EB債を発行する実務が遅れたことを隠すために一担当者がやったことで、利益を約140億円計上したいためにこのスキームを採用したのではない。」(要確認。)
・・・という主張のようです。
これに対して、証券取引等監視委員会の主張では、「そもそも連結すべきだった」という主張の模様。
---
デリバティブ等の中身の実態がわからないので何ともいえませんが、上記の一連の流れを振り返ってみると、個別の株式の取得価額合計は、
07/20 第三者割当:1,042.60億円(=5,200,000 株×@20,050円))
08/04 CSK(1) : 426.60億円(=1,580,000株×@27,000円)
08/06 CSK等 : 125.28億円(= 464,000株×@27,000円)
10/28 TOB・交換: 775.80億円(=2,770,731株×@28,000円)
で、(ざっくり)2,370億円。(10,014,731株。平均取得単価約23,668円)
当時のチャートを見てませんが、9月末時点では、株価がTOB価格に張り付いていたとすると、@28,000円×10,014,731株=約2,804億円くらいで、2004年9月末半期で、すでに、430億円くらいの含みはあった、と考えられます。
つまり、経済的実態としての時価で考えれば、ベルシステム24の株式は、それなりの価値はあったし、実際に、後で高値で売却できている模様。
ただし、2004年9月の半期末ですでに71.73%を保有していて(単体でも)「子会社株式」ということになりますし、連結するとなると、時価会計は適用されず「取得原価」で計上すべき(利益は計上されない)、ということになります。
「売買目的有価証券」であれば、上場株式は時価で評価して貸借対照表に計上するとともに、キャピタルゲインも計上できるわけですが、売買目的有価証券の要件を満たさないはず。(100%取得して非上場化を目的としているので・・・。)
で、「ベンチャーキャピタル条項」を利用した、ということかと思います。
---
さて、EB債とかデリバティブとか言われているものの中身がわからないわけですが、このデリバティブの性質を、株価の変動によりベルシステム株を代わりに得られる債券であって、最終的なTOB価格28,000円より低いstrike priceのコールオプションのようなものだと仮定してみましょう。
本日の日興さんの記者会見では、上述のとおり、「本来8月に決議するはずが、9月になってしまって、その間の利益が計上されてしまった。利益を水増しする意図は無かった。」とのこと(らしい)ですが、8月はじめには、3分の2超の株式の取得が決まって、この先、TOBをして非公開化するのは確実、というときです。
TOBをしたら通常、直前の株価の10%以上のプレミアムがつけられるのは確実。
3分の2超取得して産業活力再生特別措置法の認定も取れそうということであれば、(良かれ悪しかれ)少数株主は実質的にTOBに応じざるを得ないわけで、TOB価格もある程度自由に決められたはず。
TOB価格で株価が上がって確実に損をするようなデリバティブの契約を、子会社であるSPCが100%親会社と締結する、というのは、どう考えても、8月時点で経済的合理性があった取引とは考えにくいですよね。(下記追記:ホントにそうか?参照)
8月中でなく、9月になってTOBの条件等の着地が固まってから、
「実態は430億円も含みがあるんだから、何とかこのうちの一部でも、当半期の利益に計上できないの?」
「じゃ、8月にバックデートして、こういうデリバティブを組んだとしたら、当半期に利益計上するという理屈も立つんでは?」
などということで、(アメリカで今年問題になった、ストックオプションのbackdating的に)このスキームが組まれた・・・かどうかは今後の開示を拝見しないとわかりませんが、第三者間では説明が付かない取引であれば、そういう風に思われてもしょうがないかも知れません。
とにかく、このデリバティブの中身の開示もされてない段階で、仮定に基づいた話ではありますので、実際には誰にどんな責任があったかは定かではありませんが、以上、ご参考まで。
(ではまた。)
追記:ホントに第三者間では行われないような取引か?ということについて、別エントリを立てました。
2300億円もペーパーカンパニーに貸し付けるリスクを考えれば、140億円くらいのリターンを求めるというのはありうるかも知れません。